
 Top
Top医療の挑戦者たち 18
人工心臓の夢
大空の英雄が実現させた二度目の「世界初」は、
人工心臓の夢をひらいた。
チャールズ・リンドバーグ
「なぜ、彼女の心臓弁を交換できないのか。ポンプのような機械を使って、血液を全身に送れば、その間に心臓を取り出して手術できるのではないか」。青年は医師に食い下がった。しかし、満足な回答は得られなかった。
彼は一九二七年、ニューヨークからパリまで、飛行機による世界初の無着陸大西洋横断を単独で成し遂げた英雄、チャールズ・リンドバーグ。二五歳にして、不可能を可能にした彼には、心臓弁膜症の義姉が弱っていく姿を、ただ見守るという発想はなかった。
彼は、その医師にアレクシス・カレル博士を紹介される。フランスから渡米した医学者・カレルは、血管をつなぐ方法の開発や臓器移植実験により、アメリカで初めてノーベル賞を受賞していた。カレルは、「一時的に使える人工心臓は実現できるかもしれない。ただ、それができたとしても、取り出した本物の心臓を生かしておく方策が必要になる」とアドバイスした。リンドバーグは、カレルの研究室に通い、持ち前の工学技術を駆使して、切り離した臓器に培養液を供給することで生かしておく「かん流ポンプ」の設計をはじめた。
一九三五年、彼は動物の臓器を、体外で長期間生かすことに成功する。これは、彼が成し遂げた二度目の「世界初」となった。だが、その一年前、義姉は帰らぬ人となっていた。
リンドバーグが思いついた「心臓の代わりをするポンプ」の考え方は後世に引き継がれ、人工心臓はすでに実用化の時代を迎えている。
(監修 / 川田志明 先生 慶応義塾大学 名誉教授・山中湖クリニック理事長)

飛行家の工学的な発想と
外科医の知識が結びついて目指した「人工心臓」
飛行機のエンジンを積み替えるように
アメリカのセントルイスで郵便飛行機のパイロットをしていたチャールズ・リンドバーグは、懸賞金付きの飛行レースに応募し、見事にニューヨーク・パリ間をノンストップで飛んだ。
英雄となった彼だが、飛行機に乗るたびに周囲が大騒ぎをする環境が煩わしくなり、やがて興味は医学や生物学といった方向へ向かっていった。その大きな理由は、妻の姉が心臓弁膜症で、どんどん衰弱していくのを何とかしたいという思いからだった。彼は、飛行機のエンジン弁が故障したケースを思い浮かべ、義姉の心臓を取り出して修理している間、心臓の代わりをするポンプのような機械で体を生かし続け、その後、修理済みの心臓を体に戻すことはできないかと医師に相談した。このエンジンを積み替えるような考え方は、いかにも飛行機乗りらしい、工学的な発想といえる。しかし医師はそれに答えることができず、代わりにノーベル賞学者のカレルを紹介した。*1
(*1 Berg LA:Lindbergh,Berkley Books, 1999より)

チャールズ・リンドバーグ
(Charles Lindbergh, 1902-1974)
(Charles Lindbergh, 1902-1974)
組織培養から臓器培養へと進展したカレルの研究
フランスの外科医、アレクシス・カレルは、血管を縫い合わせる「血管縫合」と、血管同士をつなぎ合わせる「血管吻合(ふんごう)」に大きな業績をあげ、渡米した。そして1912年、彼は血管縫合と臓器移植の業績により、米国在住者として初のノーベル生理学・医学賞を受賞した。その後1920年代には、組織培養を基礎に、臓器そのものを培養することへと、彼の研究は進展していった。リンドバーグのアイデアはカレルの興味を引くところとなり、二人による共同研究が開始されたのだ。その目標は、一種の「人工心臓」ともいえるものの実現だった。

アレクシス・カレル
(Alexis Carrel 1873-1944)
(Alexis Carrel 1873-1944)
無着陸大西洋横断で「世界の英雄」に
飛行機に魅せられて
リンドバーグはスウェーデン移民の子であったが、父親は弁護士として成功し、下院議員となった。4台の馬車を所有し、食事はコックが作るという裕福な家で、家族は非常にプライドが高かった。彼自身は思慮深い少年だったが、孤独癖が強く、また独立独歩の人間になるよう育てられていた。そのためか、幼年時代からハイスクール卒業まで、友人がいたという記録は見当たらない。彼は大学の工学部に進んだが長続きはせず、私立の飛行学校に転校。そこで初めて夢中になれるものとして「飛行機」に目覚め、友人もできるようになる。その後、陸軍の飛行学校に入り、猛勉強をして首席で卒業した。リンドバーグは、飛行機によって、たくましい青年に生まれ変わったのだ。
大西洋無着陸横断に挑む
卒業したリンドバーグは、航空郵便のパイロットとして働いていたが、同じ経路を飛ぶ単調な生活に飽きてきた。そこに、複数のホテルを所有する資産家が、ニューヨーク・パリ間をノンストップで飛んだ者に2万5千ドルの懸賞金を出すと発表。多くの飛行家が一番乗りをめざす事態となった。何人ものクルーを組んだ大型の飛行機が次つぎに失敗する中、1927年、リンドバーグはたった1人で、小さな単発機「スピリット・オブ・セントルイス号」に乗りレースに挑戦した。燃料タンクをいくつも増設し、フロントウインドウの手前にもタンクを増設したため、ほとんど前方の視界がなくなるという大改造で、愛機は、さながら「空飛ぶ燃料タンク」の様相を呈した。そして、ひと包みのサンドイッチを持ち、何の通信手段も持たず、彼はニューヨークを飛び立った。大西洋横断レースの成功率を10%と計算していたロンドンの保険会社も、リンドバーグの場合は危険すぎるので、成功率の発表は控えるとの声明を出した。
横断飛行の成功で世界中が大騒ぎに
やがてアイルランド沖を航行していた汽船から、小型機が東に向かっているという連絡が入ると、世界中は大騒ぎになった。ウォール街では強気の株取引が展開され、過去1年半で最高の出来高を達成した。横断飛行成功率の数字を出さなかったロンドンの保険会社は、いまさらではあるが「成功率は30%」と発表した。深夜の東京では、数千人が街頭に繰り出したとも伝えられている。フランス政府はシェルブールなど、リンドバーグが着陸しそうな飛行場の夜間照明をすべて点灯するよう命じた。ニューヨークを飛び立ってから33時間30分、彼はル・ブルージュ空港に着陸した。待ち構えた15万もの群衆が、一斉に飛行機をめがけて押し寄せた。機転を利かせたフランス人がリンドバーグの飛行帽を奪い、近くにいた新聞記者にそれをかぶせると、群衆がそちらに殺到したため、リンドバーグは無事に脱出できたと伝えられている。彼は、完全に世界の英雄になっていた。*1

リンドバーグの無着陸大西洋横断飛行の成功を報じる新聞
義姉の心臓を手術する方法としてリンドバーグが考えたのは「ベンチサージェリー」だった
心臓弁膜症だったリンドバーグの義姉
妻の姉は、町でも評判の美貌ぶりだったが、リウマチ性の心臓弁膜症を患っていた。僧帽弁(そうぼうべん)の働きに異常があったとされており、おそらく弁がしっかり閉じないため、全身に供給される血液の量が少なくなり、体が弱っていったものと考えられる。
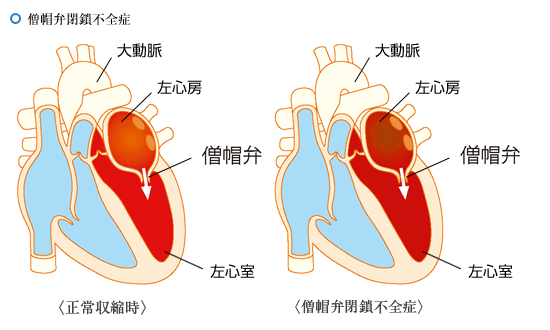
僧帽弁がしっかり閉じないため、左心室から左心房へ血液が逆流し、
その分だけ全身に供給される血液の量が減る。
その分だけ全身に供給される血液の量が減る。
臓器を取り出して治療する「ベンチサージェリー」
現代の心臓弁手術は、そのほとんどが心臓を体に残したまま治療する形をとっている。しかし心臓を開いての手術そのものがほとんど行われなかったこの時代、リンドバーグは、病気の心臓をいったん体から切り離して手術する方法を想定したのだ。その手術の間、心臓を失った体には、機械式のポンプで血液を流しておき、心臓の治療が終わったら、それを再び元の体に戻すというわけだ。
この方法は、現代の「ベンチサージェリー」そのものである。台(bench)の上で外科治療(surgery)をするのがベンチサージェリーで、移植医療ではこの方法がとられている。臓器提供者から切除した臓器は、台に載せた容器の中で冷やされながら臓器保存液などで、かん流(液を通す)され、移植に適した状態に準備される。そして患者に移植されるのだ。また腎臓などのがん手術でも、ベンチサージェリーを用いることがある。患者の腎臓を切り取り、がん病巣を注意深く見極めて取り除いた後、その腎臓を自家移植するのだ。リンドバーグは、ベンチサージェリーの先覚者といえるのかもしれない。
「Glass Heart」は人工心臓か?
かん流装置の開発に没頭
ベンチサージェリーを前提に考えていたリンドバーグは、「心臓を切除した体を生かしておく血液ポンプができても、心臓をかん流する装置がなければ、手術はできない」というカレルのアドバイスに従い、培養液を送ることで臓器を生かし続ける、かん流装置の設計に没頭する。*2
カレルの研究室には、腕のいい吹きガラスの職人がおり、リンドバーグが設計するかん流装置を、次つぎに製作していった。装置を作る上で最も気を使う点は、臓器の感染対策だったが、開口部に消毒済みの綿球を詰めるなどの地道な改良により、それも解決していった。
不幸を乗りこえて、かん流装置を完成
<その後、リンドバーグの研究は中断する。それは、最愛の息子が誘拐され、殺害されるという事件が起こったからだ。それに次いで、心臓病の義姉も、心臓病が悪化して亡くなった。しかしリンドバーグは、家族の不幸を乗りこえて研究を再開する。そして1935年、世界で初めて、動物の臓器をまるごとガラス容器の中で18日間培養することに成功した。*2
新聞や雑誌は、英雄リンドバーグが成し遂げた2度目の快挙を大きく取り上げ、人工心臓「Glass Heart」の発明と報じた。/p>
(*2 Friedman DM:The Immortalists, Harper Collins e- Books, 2009より)

リンドバーグの臓器かん流装置
上が臓器室で下が培養液室。か
ん流するときは小型のポンプに
つながれ、拍動する空気の圧力
で培養液が循環する。(Malinin
TI: Texas Heart Institute J.,
23, 1, 1996より)
「ガラスの心臓」と報じられたかん流装置
いまの医科学からみて、この装置を「人工心臓」といえるかというと、疑問かもしれない。現代の人工心臓は、弱った心臓を補助するタイプと、心臓を切除してその代わりを務めるタイプがあるが、いずれも血液を全身に送る機能を果たすことに変わりはない。リンドバーグのかん流装置は、培養液を臓器に送るためのもので、いまの人工心臓とは大きく異なる。しかし、もともと心臓が血液を送り出すのは、酸素や栄養を全身に届けて、臓器や器官の活動を支えることが目的である。リンドバーグのかん流装置が送り出しているのは血液ではなく培養液だが、酸素と栄養を与えることで臓器の生命活動を支えていることは確かだ。

GLASS HEARTの発明を伝える新聞



